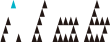Close
“Path to Innovation”は、イノベーション・コンサルティング会社i.labが運営するWEBジャーナルです。
イノベーションに関連した、アイデア創出手法やマネジメント方法、さらに、おすすめの論文や書籍について紹介します。また、注目すべき先端技術や社会事象などについても、イノベーションが発生し得る「機会」としての視点から解説していきます。
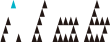

i.lab website : https://ilab-inc.jp/
Methods
「良いアイデア」とは
何か。
すぐに使える、
3つのアイデア評価軸
アイデアの「良し悪し」とは、何でしょうか。普段の生活で誰かのアイデアの「良し悪し」を厳密に考える場面はそれほど多くありません。問題となるのは、ワークショップなどチームでアイデアをたくさん出した後です。今回は、i.labで用いられているアイデアの評価方法についてご紹介します。
Issey Ishikura / 2014.12.01
みなさま初めまして。i.labでインターンをさせて頂いている、石倉一誠と申します。
最近は修士過程の研究が忙しく、i.labのコンサルテーション業務にあまり携わることができておりませんが、Web周りのお手伝いをしています。今回は、そんな私から、i.labで用いられているアイデアの評価方法についてご紹介します。
「良いアイデア」とは
さて早速ですが、アイデアの「良し悪し」とは、なんでしょうか。
「それ、良いアイデアだね」という言葉はアイデア創出ワークショップなどの中だけでなく、普段から何気なく使われる言葉です。しかし、具体的にどのようなアイデアを「良い」と感じるかは個人や場面で大きく異なりますよね。
普段の生活で誰かのアイデアの「良し悪し」を厳密に考える場面はそれほど多くありません。問題となるのは、ワークショップなどチームでアイデアをたくさん出した後です。多くの人は自分のアイデアに愛着があるためにそれがよく見えてしまいます。しかしそのように、誰もがアイデアに対してそれぞれの先入観を持った状態で議論を進め、各々が先入観を拭えぬまま時間がなくなり、その場の雰囲気でなんとなく「良い」アイデアが決められてしまう。もしかしたら皆さんも、そんな経験があるのではないでしょうか。
これが起こると、その後のプロセスで「自分は、本当は別のアイデアが良いと思っていた」とか、「なんでこのアイデアが良かったんだっけ」ということになりかねません。アイデア発想をより実りある物にするためにも、後のプロセスを効果的にするためにも、アイデアの「良さ」をチームできちんと評価することが重要なポイントになってきます。
「良さ」を評価する、3つの視点
i.labが行うワークショップでは、全てのアイデアを様々な手法を用いて公平に評価し、それぞれのアイデアが相対的にどのように違うのか、そして、それぞれのどの点が良いのかを明確化していきます。
そこで今回は、アイデアを評価する際に活用できる、最も基本的な3つの評価軸をご紹介します。
1. 新規性
そのアイデアがこれまでに見たことも聞いたこともないような斬新なものかどうか。
「斬新さ」と一言で言っても、そこには現状では賛否両論が分かれる程の切り口の斬新さがあるか、新しい要素を持つ価値や体験が得られるか、など様々な「新しさ」が含まれます。着目した問題が新しいのか、解決する方法が新しいのか、など厳密な部分にはとりあえず目をつぶり、とにかくそのアイデアを聞いた時に「あ、新しい!」と感じるか否か、そのシンプルな違いでアイデアを評価します。
2. 実現可能性
現実的に実行可能なものかどうか。
アイデアを評価する際、例えばそのアイデアを実現させようと明日から動き始めるとしたとき、実現までの筋道がそれなりに見えるかどうか、という基準で判断出来ることが多いです。
少し具体的に説明しますと、アイデア実現に必要となるリソースの実現性や、ターゲットとして想定している社会・市場の妥当性などを問うことがあります。
少しシビアな観点ではありますが、どんなに面白いアイデアでも絵に描いた餅になってしまっては仕方がありません。ただの楽しいワークショップで終わらせないためにも、非常に大切なポイントです。
3. 社会的インパクト
そのアイデアが秘めている社会的なインパクトの大小。
もしもアイデアが実現されたとしたら、どのくらいの規模の人々の生活や価値観、行動を変化させるのか。イノベーション創出のためのアイデア、という文脈で考えると、これが最も重要な点と言えるかもしれません。
この観点を持ち込むと、誰がそのアイデアを実現していくのか、という主体者の確認や実現プロセスへの視点がアイデアの評価に加わります。例えば、日本を代表する大企業が、ベンチャー企業がやりそうな奇抜でニッチなビジネスを突然始めたら、日本社会の中で、ユーザだけでなく労働者やステークホルダーなど、様々な社会にどのような影響を与えるのか。それは良い影響なのか、悪い影響なのか。
イノベーションが人々の価値観や行動に不可逆な変化を起こすものだとすれば、そのアイデアが実現されていく過程も、その影響力として評価していくべきだと私たちは考えます。
アイデア再検証が、チームにもたらすもの
以上3つの評価軸をご紹介しましたが、実現に持っていく最終的なアイデア決定の際に全ての点を完璧に満たしている必要はありません。また、どれかの軸で最も評価の高いものを選ぶ必要もありません。例えば、そのアイデアが「新しすぎる」ことは実現するにあたって大きな害となり得ますし、全てを満たしているように思われるアイデアというのは普通はありません。(あるように思えたら、残念ながらそれは前提が間違っているか、大抵既に実現されています。)
また、これらの3つの評価軸を使うことが間違いなく「良いアイデア」を選ぶわけでもありません。「良いアイデア」の定義は最初に述べたとおり場面やその後のプロセスによって変わりますので、そのプロセス設計に則った軸を用意することが肝要です。
とどのつまり、今回紹介しましたこれらの評価軸を用いて、チームメンバーが全てのアイデアを適切に評価すること。そして、選んだ一つのアイデアをチームで力強く前へ押し進めようと思えるようにすること。これらが、しっかりとした評価軸を用いてアイデアを評価する本当の意義なのです。
沢山出たアイデアをどう評価するか困った時には、これらの評価軸を使って目の前にあるアイデアを整理してみてはいかがでしょうか。
きっとそれまで見えなかった「良い」アイデアに出会えるはずです。
もし、皆さんが使っている有用なアイデア評価軸がありましたら、是非コメントなどで教えてください。
Author


石倉 一誠
Issey Ishikura
i.lab Internship